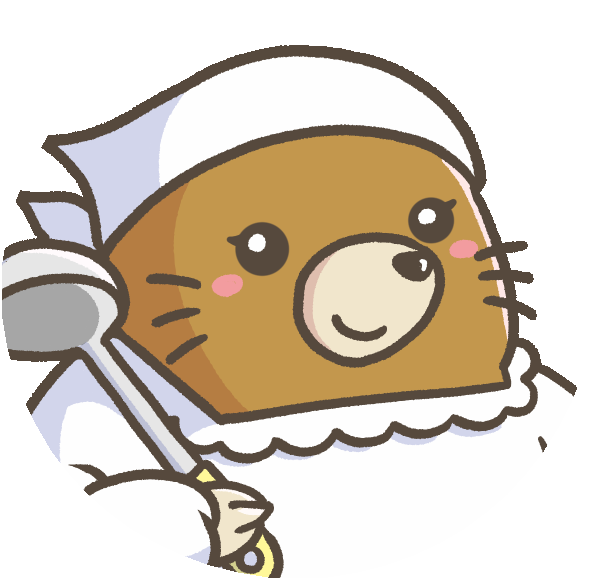
かーちゃん
こんにちは!
このブログは、子育ての話題を中心に我が家の日常を紹介してます
クスって笑ってもらったり
子育て世代の方に何か参考になることがあったらうれしいです♪♪
今日は「中秋の名月」に作って食べた、行事食のお月見団子についてのレポートです!
〇 中秋の名月?十五夜? よく聞くけどそれってなに?
〇 中秋の名月って何をする日なの?
〇 お月見団子、作ってみたい!
中秋の名月とは?
2021年9月21日は「中秋の名月」でした。
「中秋の名月」は「十五夜」とも呼ばれています。
もしかしたら、こちらを耳にする機会の方が多いかもしれません。
もともと、秋の満月を愛でる風習は中国に古くから伝わっていました。
日本では平安時代より、まず貴族の間で月見の宴が行われるようになったそうです。
その後、もともとの習慣(五穀豊穣に感謝して月にお供えする習慣)などと結びついて、庶民にも月見の風習が広まっていきました。
なお、「中秋の名月」は旧暦8月15日を指します。
したがって、今年(2021年)の「中秋の名月」は9月21日となります。
※「中秋の名月」は毎年日にちが変わるので、注意してくださいね!
さらに!
今年(2021年)は、8年ぶりに満月の日に当たりました。
中秋の名月=満月 と思われがちですが、必ずしも旧暦8月15日が満月になるわけではないのですね。
(月の満ち欠けの流れと暦の流れには時差があるため)
そんなわけで、今年「中秋の名月」を愛でることができた方はとても運が良い!
(愛知県在住の私、今年は雨天のためお月様をみることができませんでした。残念!)
「中秋の名月」の行事食とは
言わずもがな「お月見団子」です!
我が家でも、お月見団子を作って食べました。
「お月見団子」&「うさぎ」の作り方
今回は「お月見団子」と「うさぎ」の2種類作りました!

<材料>(団子約15個、うさぎ6個分)
・団子粉 150グラム

↑団子粉。特別こだわりはありません。
・砂糖 15グラム(甘さ控えめの分量です)
・食紅(赤・黄) 少々
・ぬるま湯 適量(今回は100~110ml)

↑食紅。こちらも特別こだわりはありません。
<作り方>
1.団子粉と砂糖を混ぜ、ぬるま湯を少しずつ入れます。
2.耳たぶくらいの固さになるまでこねます。
3.(お月見団子)直径2センチほどの団子を15個作ります。
生地に余裕があれば、お月様用にあと3個作ります。
※お月様用に3個作ったのは、我が家に子どもが3人いるからです。
ご家庭の事情によって個数は変えてくださいね。

4.(うさぎ)残った生地を二つに分け、ひとつには赤い食紅を混ぜます。

5.(うさぎ)それぞれ3つに分け、俵型に丸めます。
※これも、3個ずつに分けたのは我が家には子どもが3人いるからです。

6.茹でます。
最初は沈んでいますが茹で上がると浮いてくるので、浮いてきて3,4分経ってから取り出します。

7.(お月見団子) 盛り付け
丸い団子はピラミッド状に積んだら「お月見団子」の完成。
※本来お月見団子は15個積み上げますが、今回はお皿に乗りきらず写真は10個で積んでます💦

8.(うさぎ)俵型6個でウサギを作ります。
下の写真のようにハサミで二か所切りこみを入れ、ウサギの耳を作ります。

赤い食紅を水に溶かし、つまようじにつけて、耳と目を描きます。

9.(お月様)黄の食紅を水に溶かし、丸い団子3個に指で塗ります。
※お月見団子で丸い団子を使い切ってしまった場合は、この工程はないです。
団子を茹でる前に、生地に黄の食紅を混ぜてもオッケーです。

お月様とウサギ、完成!
最初生地に少しお砂糖を入れましたが、家族には少し物足りなかったよう。
砂糖醤油をつけて食べていました。(私はそのまま食べましたが)
甘めが好きなお子さんには、最初にもう少しお砂糖を入れてもいいかもしれません。
中秋の名月(十五夜)以外のお月見
お月見は中秋の名月(十五夜)以外にも、十三夜(旧暦9月13日)、十日夜(とおかんや:旧暦10月10日)と呼ばれるものがあります。
これらすべての日が晴れてお月様を拝むことが出来たら、それはとても縁起の良いことだと言われています。
「中秋の名月」のお月様が見られたなら、十三夜、十日夜のお月見にも挑戦してみてください!
子どもに伝えたい行事食☆「中秋の名月」まとめ!
☆旧暦8月15日は「中秋の名月」
お月見団子を食べながら、お月様を愛でましょう。
☆お月見は全部で3回
十五夜を見逃しても、まだチャンスはある!
☆お月見団子は材料も少なく作るのが簡単!
子どもと一緒に作れば食育にもなりますね!

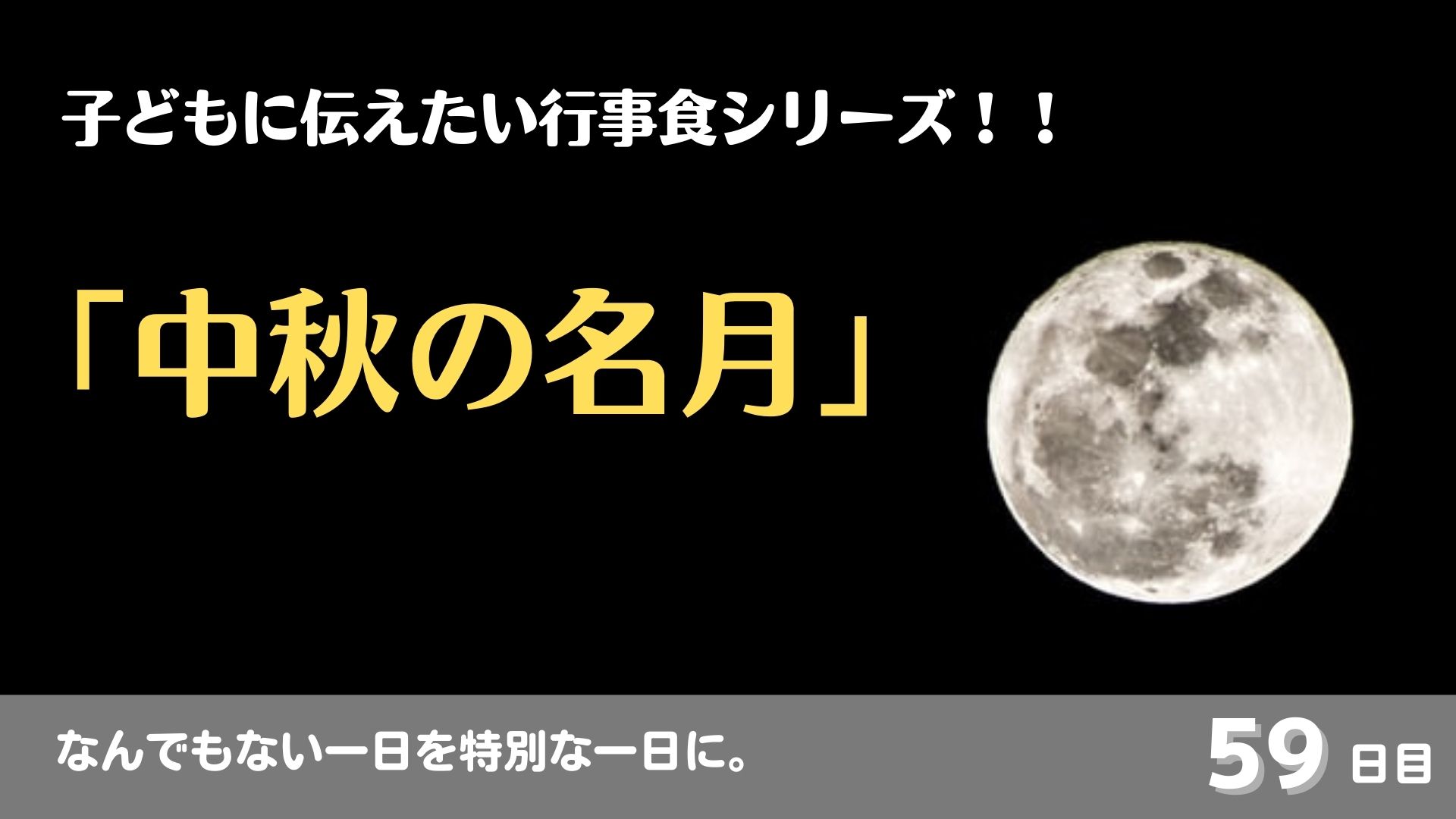
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21eef9b0.2baf5582.21eef9b1.33edadde/?me_id=1378557&item_id=10000478&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoutarou%2Fcabinet%2F07423401%2Fimgrc0088510631.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21eefed3.a1fbc5f9.21eefed4.a55b447c/?me_id=1303015&item_id=10000095&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchirimenzaikukan%2Fcabinet%2F06667439%2Fimgrc0079772794.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
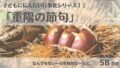

コメント