気づいたら7月が終わり、昨日からはもう8月ですね。
夏休みももう1週間が終わってしまったと思うと
なんだか気持ちが焦ります💦
さてさて。
昨日、8月1日は「八朔(はっさく)の祝い」の日でした。
「八朔」とは?
はい、もちろん柑橘系果物の「はっさく」ではありません。
「八朔」=「八月朔日(ついたち)」の略だそうです。
「八朔の祝い」は別名「田実(たのみ)の節句」とも言われ
豊作を祈願する風習とされています。
この日には
ススキの穂を焼いてお粥に混ぜた「尾花粥」や
尾花粥に似せた「黒ゴマ粥」を食べて
暑さ疲れに対応するのだそうです。
私も尾花粥を是非食べてはみたかったのですが
ススキの穂をどのように手に入れて、どのように焼いて
どのように加工するのかさっぱりピーマン・・・(古っ!)
失敗して、子どもや高齢者に変なものを食べさせてもいけないので
今回は「黒ゴマ粥」で挑戦させていただきました。
<黒ゴマ粥>
作り方は・・・テキトーです( ̄▽ ̄)。
作るのは7人分ですが、我が家でお粥系はあまり人気がないので
今回は少なめで作りました。
普通に作ったお粥(今回は七分がゆにしました)に
炒ってすった黒ゴマを入れる、ただそれだけです。

↑ばぁばモグラ愛用のゴマ炒り器を借りて。
炒っていると、煙が出ると同時にゴマのいい香りがしてきます。

↑これまたばぁばモグラ愛用のゴマすり器を借りて。
炒っている時よりもさらにいい香りです。

↑少なめに作ったつもりですが、7人で分けても少し余りました。
米1合に対して、ゴマを40gほど入れましたが
適当に作った割には良い黒さ加減♪
黒ゴマはすったものを買ってこようか迷いましたが
実際自分で炒ってすってみると香りが全然違うので
こういったシンプルな料理には、多少手間でも自分で作ることをおススメします!
我が家の子どもたちも
黒ゴマの香りに誘われて、めずらしくおかわりしていました。
ゴマは老化防止にもなるのだとか。
はー、食べる前に知っていたら、もっとおかわりしたのに!

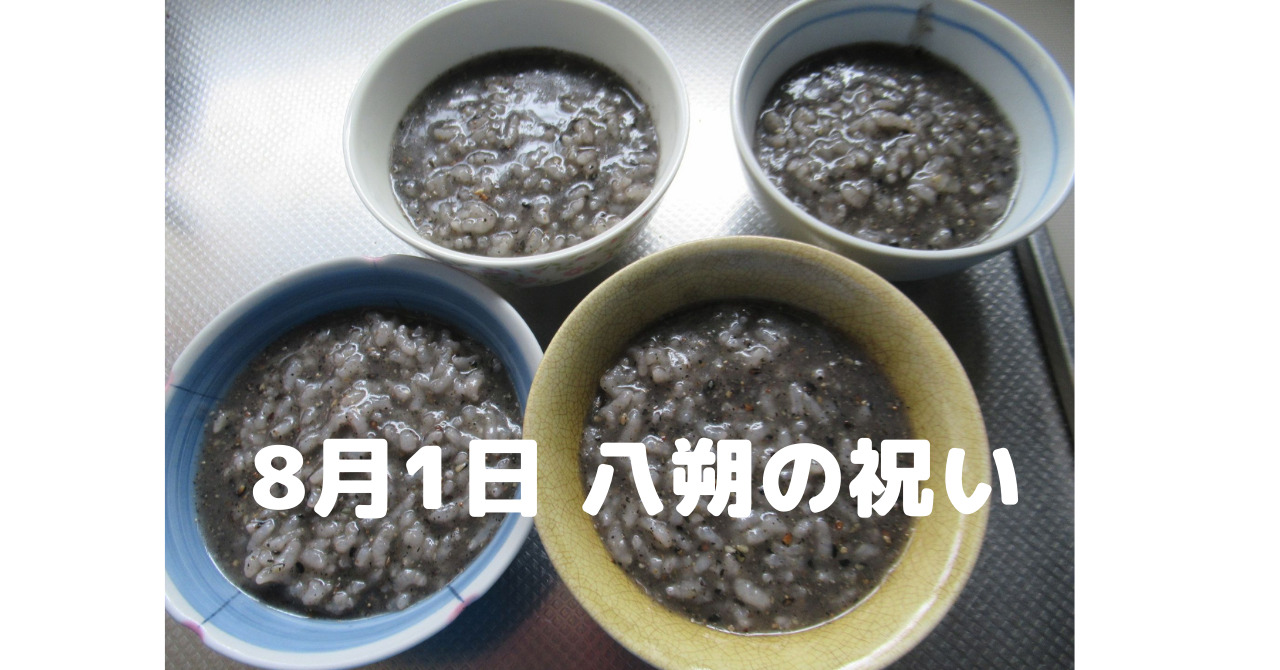


コメント